
|
|
||||||
従来の実験書で間違いや不備と思われること |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【硼砂溶液の濃度】
スライムの性質は、架橋されたPVAの分子の大きさと、架橋の密度、含まれる水の量などに依存すると推測されましたので、まずその点を確認してみました。 まず、もっとも標準的なレシピから、OH基の数と、硼酸イオンの数、および水分子の数とを計算してみると次のようになります。
子供たちにスライムを作らせていて、ホウ酸溶液をたっぷり加えても固まらないときは、迷わず洗濯糊(PVA10%)を加えた方が確実です。 「硼砂溶液が薄いと固まらない」という説が誕生した理由は、次のように推測されます。 最初にスライムの現象を発見したときには洗濯糊と適当な濃度だった硼砂溶液が混合されたのでしょう。その後、この現象を再現しようとして試行錯誤を繰り返すうちに、失敗が少なく覚えやすい方法として「洗濯糊を倍に薄め、硼砂の飽和水溶液を使う方法」と、「それぞれの4%溶液を100mlと10ml混合する方法」が一般化したものと思われます。(前者は日本、後者はアメリカの資料に多い数字)
【硼砂のスライム中での役割】
ホウ酸イオンが、アルコールのOH基に近づくと、そのOH(アルコール)の水素(H)が外れて、酸素原子の求核攻撃が起こり、CH2-O-Bの無機酸との強い結合ができて架橋されると思われます。この架橋のしくみについては私も良く分かっていないのですが、硼砂はアルコール(-OH)基の定量に使用されるほどアルコール基に強く結合します。海外の資料を見てもこの部分を水素結合としたものと、硼素の酸素の孤立電子対への求電子攻撃で説明しているものとがあります。
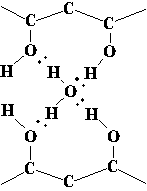 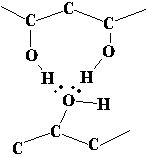 硼酸イオンと、PVAのOHとの間が水素結合という説明もありますが、硼酸イオンとOHとの水素結合が架橋の役目をするなら、右図のようにもっと強い水素結合の(すでに存在している)水分子だけで十分と思われますし、酸性にすると粘度が失われる(エステル結合が加水分解される)などから、スライム化が硼酸イオンとの単純な水素結合による架橋というだけではスライムの挙動を説明するのに不十分と思っています。 硼酸イオンと、PVAのOHとの間が水素結合という説明もありますが、硼酸イオンとOHとの水素結合が架橋の役目をするなら、右図のようにもっと強い水素結合の(すでに存在している)水分子だけで十分と思われますし、酸性にすると粘度が失われる(エステル結合が加水分解される)などから、スライム化が硼酸イオンとの単純な水素結合による架橋というだけではスライムの挙動を説明するのに不十分と思っています。
【PVAでなければだめか?】 PVA(ポリビニルアルコール)でないとできないとしている実験書もありますが、酢酸ビニル-[CH2-C(H)OCOCH3]-でも架橋は起きそうなので、手元にある酢酸ビニルエマルジョンでも試してみましたら、(エマルジョンは濃度から薄いので、薄めずに硼砂溶液を加えました。)色は白いですが固まりました。 PVA(ポリビニルアルコール)でないとできないとしている実験書もありますが、酢酸ビニル-[CH2-C(H)OCOCH3]-でも架橋は起きそうなので、手元にある酢酸ビニルエマルジョンでも試してみましたら、(エマルジョンは濃度から薄いので、薄めずに硼砂溶液を加えました。)色は白いですが固まりました。必ずしもPVAでなければという物ではありません。 【衣服についたらどうする?】
我が家でも子供が学校からもって帰ったときにベッドの上においていて失敗したので、衣類についたときの簡単な処理を見つけておかなければと思いました。そこで目をつけたのが酸性にすると架橋がはずれる現象で、身近な酢で試すといとも簡単に洗い流すことができました。(^.^) あまり簡単なので皆さんはもう発見ずみかも・・・・・
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||